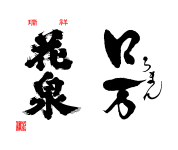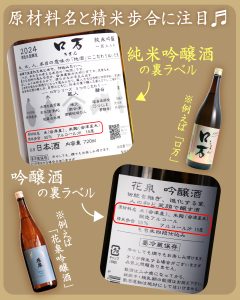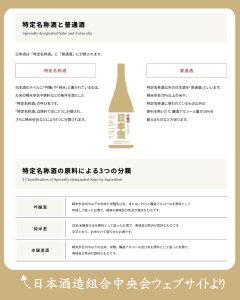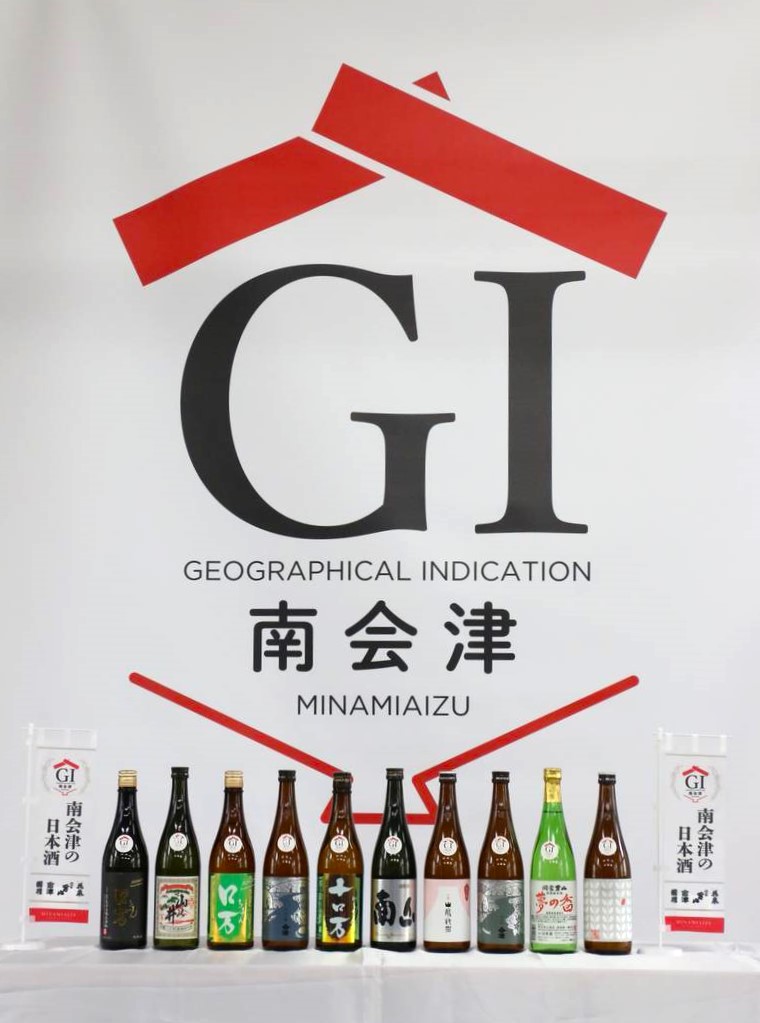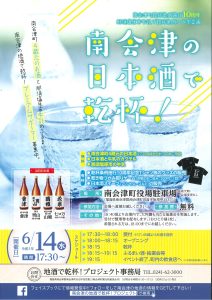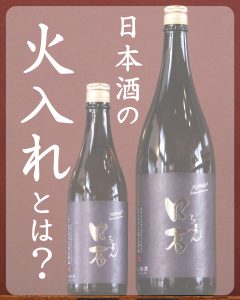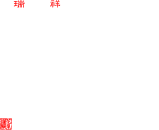2024年12月、日本の『伝統的酒造り』が
ユネスコ無形文化遺産に登録されました。
1周年を機に、登録に至ったポイントをまとめてみました。
少し長くはなりますが、
お時間のある時などにお読み頂ければ幸いです。
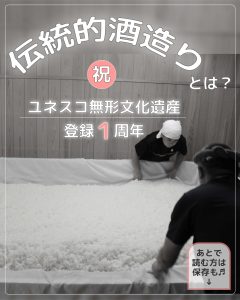
さて、ユネスコ無形文化遺産とは
世代を超えて受け継がれてきた芸能や技術など
“形のない文化”を守るための国際的な仕組み。
『伝統的酒造り』は日本で23件目 🌏
日本の食文化としては
「和食」に続く2件目🏅の登録となりました。
杜氏(とうじ)や蔵人(くらびと)がこうじ菌を用い、
長年の経験を重ねて築き上げてきた『伝統的酒造り』の技術。
その原型は500年以上前に確立したとされ、
地域の自然や風土に合わせて発展を遂げて
祭事や婚礼など日本文化とも深く結びついています。
登録にあたっては
🌱原料米や清らかな水を確保するための環境保全や
🌾地域社会との繋がり
🔄酒粕などの副産物の資源活用など
酒造りを通じたSDGs(持続可能な開発目標)への貢献も評価されたそうです。
例えば花泉酒造では、
🌱地元契約農家のお米と地元の清水を使用し、
🌾米糠や酒粕は、肥料や食品の原料として
🔄地域で再利用して頂いております。
地域の恵みと人々の繋がりがあってこそ続けられる酒造り。
今後もそのことに感謝しながら、
世界に誇れる技術と
伝統を継承する担い手となり、
美味しいお酒造りをお届けすべく、尽力して参ります。
ぜひこの機会に、日本酒を味わってみて頂ければ嬉しいです。
●最新情報はこちら
Instagram
facebook
●その他の「酒造り・日本酒用語について」はこちら
花泉ライブラリー
●参考URL
▼政府広報オンライン
「ユネスコ無形文化遺産に登録された日本の「伝統的酒造り」のわざと魅力」
「Traditional knowledge and skills of sake-making with koji mold in Japan」
https://www.gov-online.go.jp/hlj/ja/march_2025/march_2025-00.html
▼国税庁特設サイト「伝統的酒造り」
https://www.nta.go.jp/traditional_sake_making/index.htm